| 1:広がりゆく原子核物理の対象
日常目にする全ての物質は原子からできています。この原子の中心には、プラスの電荷を持った原子核があり、その電荷を打ち消すだけ電子が原子核の周りに存在します。周期律表にみる元素の多様性は、どのような原子核が存在し得るか、また宇宙創生から現在までに、どのように原子核が作られてきたかに支配されています。周期律表にある原子番号に上限があること、ある特定の元素に属する原子の同位体が無数にあるわけではないことなど、原子核を構成する陽子と中性子がそれぞれの個数で束縛状態を作れるかどうかは、自然の法則や宇宙の歴史が支配するところです。
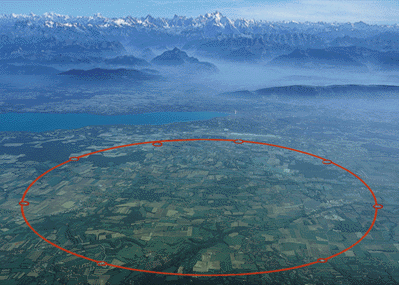
図1:スイスとフランスにまたがる欧州原子核研究所 (CERN)
の新しい加速器LHC (Large Hadron Collider) の計画。後方はヨーロッパアルプス。写真提供は、 CERN-LHC。 |
|
ところが、近年の加速器実験技術の発達は、通常の状態から遠く離れた原子核のありようを覗くことを可能にしました。ある陽子数に対して中性子が非常に多く束縛した
中性子過剰核、陽子と中性子の他に超核子(ハイペロン)と呼ばれる粒子がついて出来た
ハイパー核に関する実験は国内では 理化学研究所や 高エネルギー加速器研究機構
の加速器を用いて精力的に続けられています。更に、高密度にもかかわらず、ゆるく束縛しているゆえに液体に例えられる通常の原子核に大きなエネルギーを持ち込むことで作られる、陽子や中性子などからなるハドロン気体、その陽子や中性子自身がクォークやグルーオンと呼ばれる構成子に分解されたプラズマ状態(
クォーク・グルーオン・プラズマ
)も現代の原子核物理学の研究対象です。実験技術の進歩により姿をあらわしたこうした原子核の驚くべき多様性は原子核物理を非常にアクティブなものとしています。
| 紙面の限られたこのコーナーでは、ハドロン気体の研究に話題をしぼって紹介したいと思います。他の話題については当研究室の
ホームページの「 研究室の研究分野」・「研究成果報告」を御覧下さい。
2:高エネルギー原子核実験
さて、通常の原子核に留まらない様々な核子(陽子・中性子)からなる物質の様々な存在様式を模式的に示したのが下の相図です。
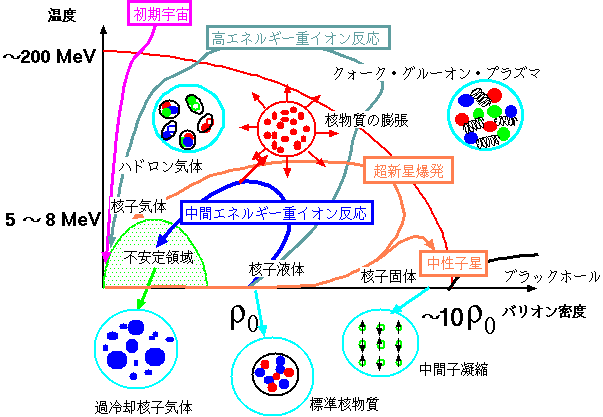
図2:様々なバリオン(=陽子・中性子)密度と温度を持つ核物質とその存在形態横軸には物質の密度を通常の原子核密度ρ0
(=3 x 1014g/cm3)を単位にして示し、縦軸には温度をMeV単位(1 MeV
=1010K)で示した。
通常の原子核(標準核物質と記されている)から遠く離れた核物質は、自然界では 初期宇宙 や 中性子星
といった対象で実現します。これらの状態を実験室で実現するのが 高エネルギー重イオン反応実験です。重イオンとは原子から殆んどの電子をはぎとったもので、これを加速して衝突させると、高温高密度の原子核が一瞬だけ生成されます。この実験の究極の目標は前述したクォーク・グルーオン・プラズマの生成であり、ドイツの重イオン研究所(GSI)、アメリカのローレンスバークレイ国立研究所(LBNL)や ブルックヘブン国立研究所(BNL)、 欧州原子核研究所(CERN)
といった各地の研究所がエネルギーを上げながら競ってこの生成を目指して来ました。バリオン(核子)密度がゼロの場合、温度が150MeV〜200MeVのところでプラズマへの相転移が起こることが格子QCD
と呼ばれる数値実験で示されています。
3:粒子自由度の増大が引き起こす温度上昇の鈍化
ところがエネルギーを上げたにもかかわらず、期待されていたプラズマ状態はなかなか検出されませんでした。これは核物質の温度は期待されたほどには上昇しなかったからだと考えられます。エネルギー密度の高い原子核気体(ハドロン気体)を作ると、陽子や中性子の他にパイ中間子と呼ばれる粒子、更には、励起状態にある(陽子や中性子とは区別される)様々な種類の粒子が出現します。この自由度の増大は、単原子分子より二原子分子の方が比熱が大きいのと同じで、比熱の増加を招きます。エネルギー密度を上げれば上げる程、粒子自由度が増えるために、原子核気体の極限の温度(その温度以上には熱されない)という概念も生まれました。実際のプラズマへの相転移の中でどのように自由度が振舞うのかは興味深い問題です。
4:微視的シミュレーションによる核反応の研究
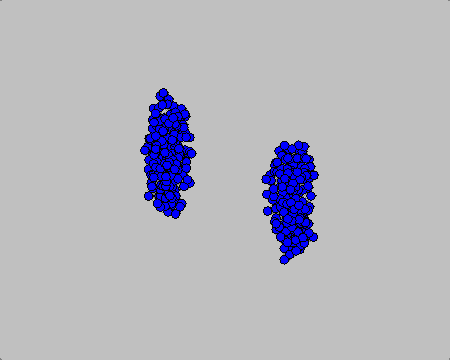
図3:2つの金の原子核が光速の72%で衝突する様子
(197Au(11.6AGeV/c)+197Au)
|
|
このような核物質の熱統計的性質を解明する一つの方法は統計力学的手法です。しかし、原子核衝突のような短時間で時間発展する高温高密度核物質が平衡状態に達しているかどうかは自明ではありません。そこで我々はシミュレーションの手法を導入します。この方法は原子核を点粒子の集合と考え、それぞれの点粒子の運動を調べるもので、
平衡状態の仮定を必要としないのが特徴です。高エネルギー原子核衝突では、核子の運動量の大なるゆえにそのド・ブロイ波長は核子の間の距離の目安である1fmよりも小さくなります。このことは核子を古典的な粒子として取り扱うことを良い近似とします。初期状態としてビームと標的の原子核の形に配置した点粒子の集合を用意し、金の2つの原子核を光速の72%の速さで衝突させた様子を計算して示したのが右の図です(これは、ブルックヘブン研究所のAGS加速器で行われた実験系に対応しています)。
|
衝突の初期の状態では左右から原子核がやってきます。 ●は原子核を構成する核子(陽子・中性子)を表します。本来は丸い原子核ですが、相対論の効果によって、原子核は進行方向に大きく収縮して見えます。
衝突後するとまず核子(●)の幾つかは核子の励起状態である共鳴バリオン(●)に変わります。これは核子がその励起状態にある別の種類のより重い粒子に変化したことを示します。
E=mc2という関係にしたがって、粒子の運動エネルギーは一旦、重い粒子の生成という形で蓄えられます。この共鳴粒子(●)は、有限の寿命をもって崩壊し、元の核子(●)に戻ります。崩壊の時に放出される●で表されている粒子はパイ中間子です。この反応を通じて394個の核子系の衝突から500個を越える中間子が生成されています。
5:粒子生成機構のモデル化
このエネルギー領域の核反応のダイナミクスを支配する大きな要因はアニメーションに示されるような構成粒子同士の衝突(素過程)における粒子生成機構です。シミュレーションの中で起こるそれぞれの構成粒子同士の衝突やそれに伴う粒子生成は、陽子+陽子衝突実験やパイ中間子+陽子衝突実験から決定されます。しかし、高エネルギー反応では引き続く衝突の効果で、構成粒子同士の反応の最中に現れる不安定な中間状態粒子が衝突を起こすこともあり、
これを実験で完全に決定することは困難です。それゆえ、シミュレーションを行うためにモデルを設定する必要が生じます。例えば構成粒子の衝突を経た粒子生成の機構として、
- 衝突後、一旦、重い励起状態(●)を作り、これを一定時間の後に崩壊させて元の核子(●)に戻し、その際に中間子(●)の生成を行う方法(右図の上の方法)
- 衝突と同時に粒子を生成させる方法(右図の下の方法)
の2通りが考えられます。第1の方法によれば粒子自由度として通常の粒子の他に重い粒子 (●)の自由度が加わるので、第2の方法に比べて、
- 比熱が大きくなるため、同じエネルギー(熱)を与えても 物質全体の温度が上がりにくくなり、
- また、エネルギーがいったん質量の形で蓄えられるので膨張の スピードが遅くなる、
などのことが期待されます。 |
|
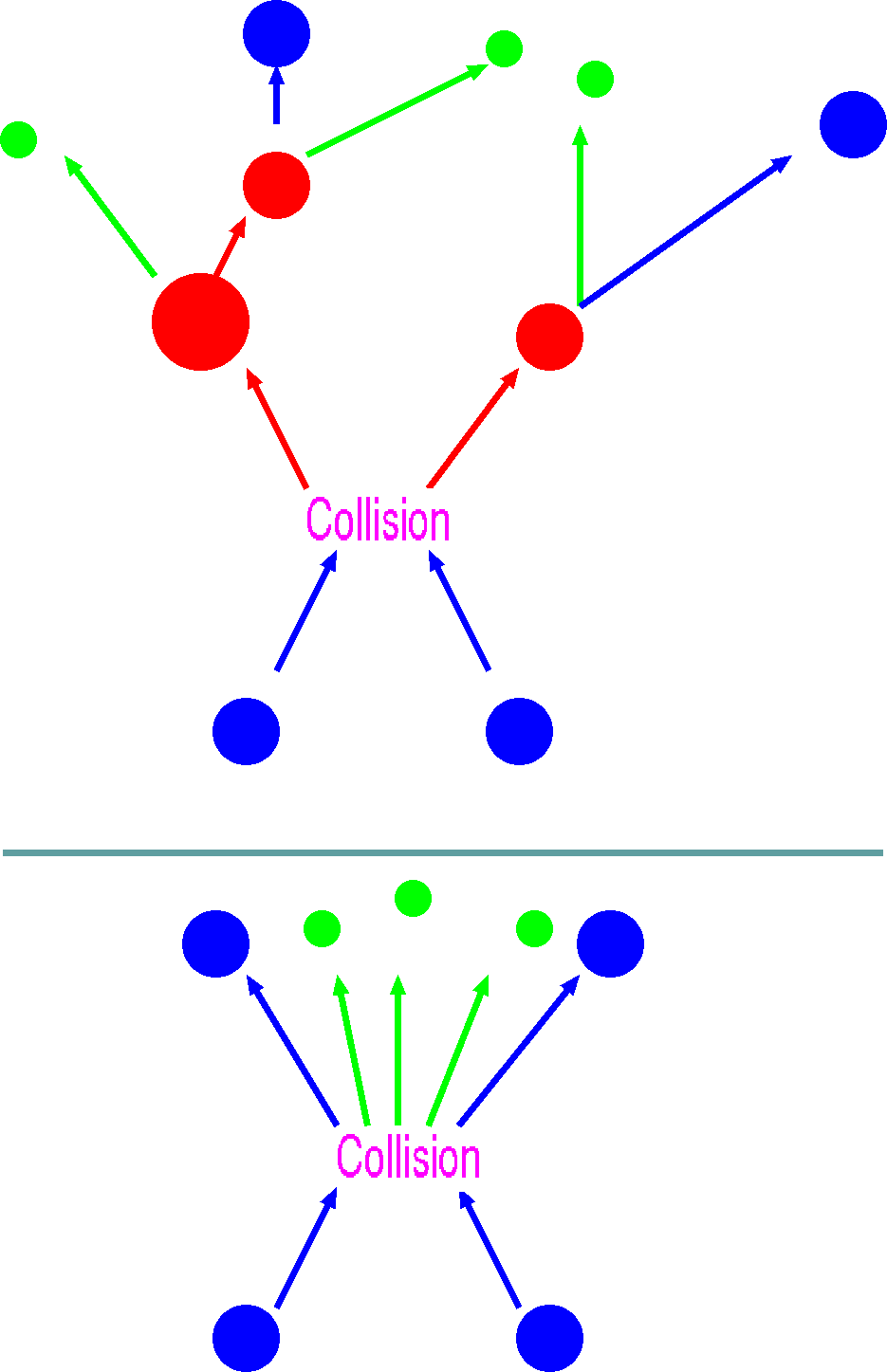
図4:2つの粒子衝突モデル−中間に重い励起粒子の存在を仮定した粒子生成と仮定した粒子生成
|
素過程での粒子生成機構モデルの導入にはこのような選択の余地が残されますが、原子核衝突実験での最終的な粒子の測定量(生成粒子量、運動量分布など)にはモデルによる差が見えるかも知れません。つまり、「重イオン衝突実験から素粒子の自由度の大きさを測る」ことが可能かも知れないのです。少なくとも、実験では見えにくい「衝突の途中」では、こうした粒子自由度の差が現れているようです。
6:シミュレーションに見る自由度の違いの熱的性質への現れ
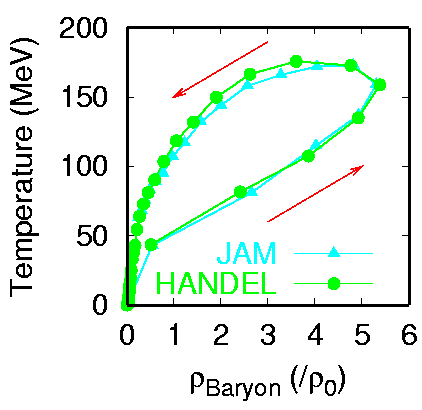
図5:2つの粒子生成モデルによる核物質の熱的発展の違い。横軸には物質の密度を通常の原子核密度ρ0
(=3 x 1014g/cm3)を単位にして示し、縦軸には温度をMeV単位(1
MeV =1010K)で示した。 |
|
図5は、重い粒子の自由度の存在を多数仮定したモデル(JAM)と自由度の存在を少数だけ仮定したモデル(HANDEL)で記述される、衝突中心付近の核物質の核子密度と温度の衝突後の時間発展を1fm/c(=3
x 10-24秒)
という時間ごとに示して、比較したものです。横軸は核子密度を通常の原子核密度ρ0を単位に取り、縦軸に温度を取ったもので、図1と同じ物理量を表しています。
衝突で得られる核物質の時間変化は自由度の導入の仕方により少し違って見えることが分かります。衝突後圧縮されてもっとも密度が高くなった状態からゆっくりと膨張していく過程では局所的な熱平衡が実現していると考えられますが、両者を比べると、まず重い励起粒子の自由度を沢山採り入れたモデル(JAM)の方が温度の上昇がほんの少しですが抑えられています。より顕著な違いは、同じ時間間隔で点を書いているのに
JAM
の方が点の間隔が小さい、つまり膨張が遅くなっているのです。これらは先に述べた粒子自由度の効果(比熱とスピード)が、この衝突でも見えていると考えることが出来ます。
|
7:今後の展開
| 現在、上で計算したAGSに加え、欧州原子核研究所のSPS (Superconducting Proton
Synchrotron)
と呼ばれる2つの加速器によるデーターが出揃いつつあります。ただし、原子核気体がプラズマに転移したという確証は得られていません。
1999年10月4日にはAGSを前段加速器とした新しい加速器 RHIC (Relativistic Heavy
Ion Collider)
が完成し、現在のテスト運転を経て2000年には実験が開始される予定です。従来の実験は静止した標的にビームを当てて原子核衝突を行わせていましたがRHICでは2つの加速されたビームを衝突させるために重心でのエネルギーが従来の実験に比べて飛躍的に増大しています。
|
|
| 年 |
加速器 |
反応系 |
エネルギー
|
|
| 1987 |
AGS |
Si+Au |
5 GeV |
| 1987 |
SPS |
S +Pb |
20 GeV |
| 1992 |
AGS |
Au+Au |
4 GeV |
| 1994 |
SPS |
Pb+Pb |
17 GeV |
| 1999 |
RHIC |
Au+Au |
200 GeV |
| 2004 |
LHC |
Au+Au |
6.3
TeV |
表1:年とともに増大する衝突エネルギー、2つのビームを衝突させる最後の2つの実験でエネルギーが飛躍的に上昇していることが分かる。エネルギーは重心系での核子あたりの値。1GeV=1025cal。
LHCは計画中。
| このRHIC実験や現在計画されている欧州原子核研究所の LHC (Large Hadron Collider)
計画がプラズマ生成への相転移を確認することが期待されます。これらの加速器がつくり出す高いエネルギーのガスの中で粒子の種類の増加が熱的性質にどのように反映され、またプラズマへと開放されていくのか、今後の研究成果の待たれるところです。
| 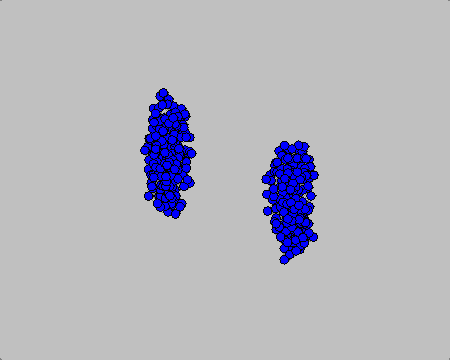 Topics
Topics 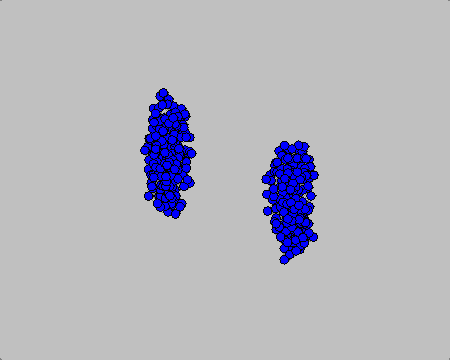 Topics
Topics